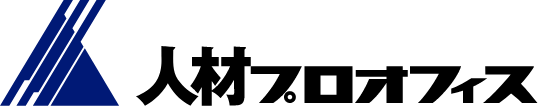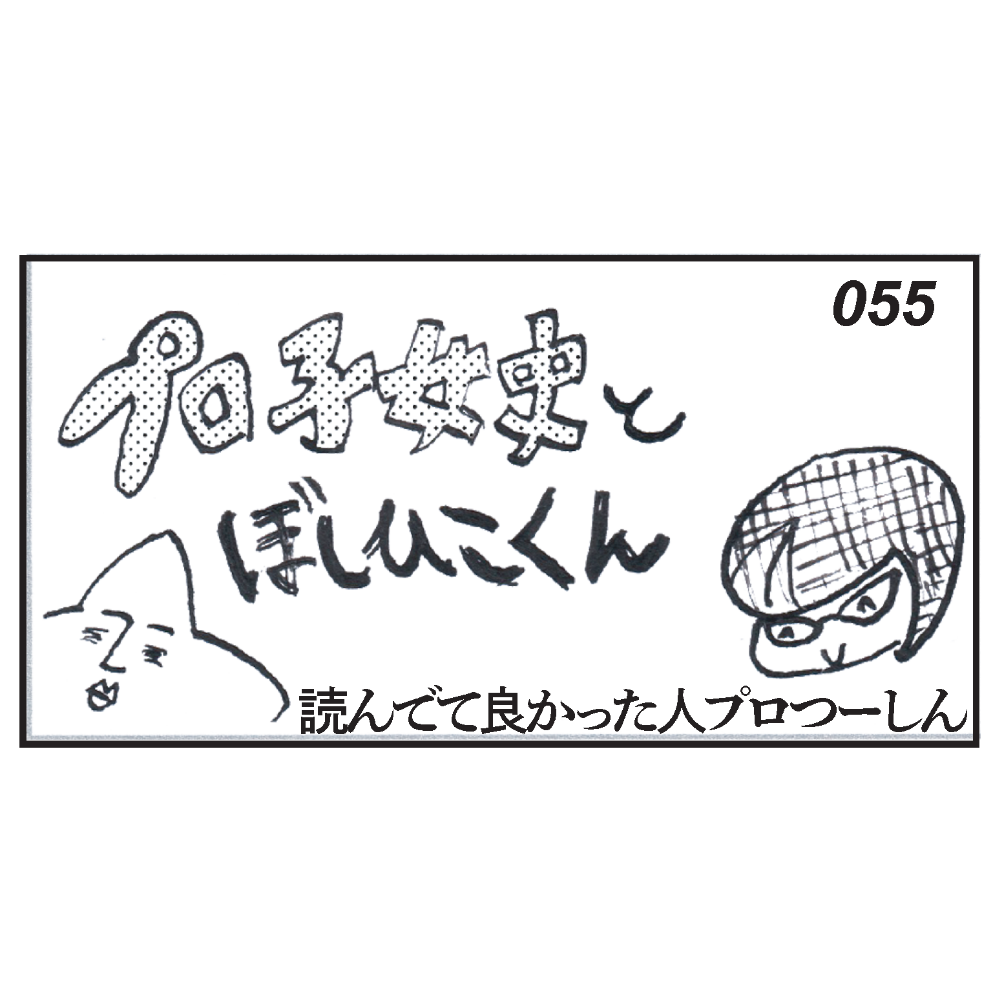地震が来たらどう対応するか
今だから考えておきたい企業としての備え
熊本地震発生を受けて
平成28年4月16日、熊本県熊本地方を震央とする最大震度7の熊本地震が発生しました。平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が記憶に新しい中での今回の地震。企業が事前に備え。考えておくべきことはなんなのでしょうか?
人材プロオフィスキャラクターの「プロ子女史」を先生として、枚方つーしんキャラクター「ぼしひこくん」が質問をしていく会話形式で見ていくことにします。
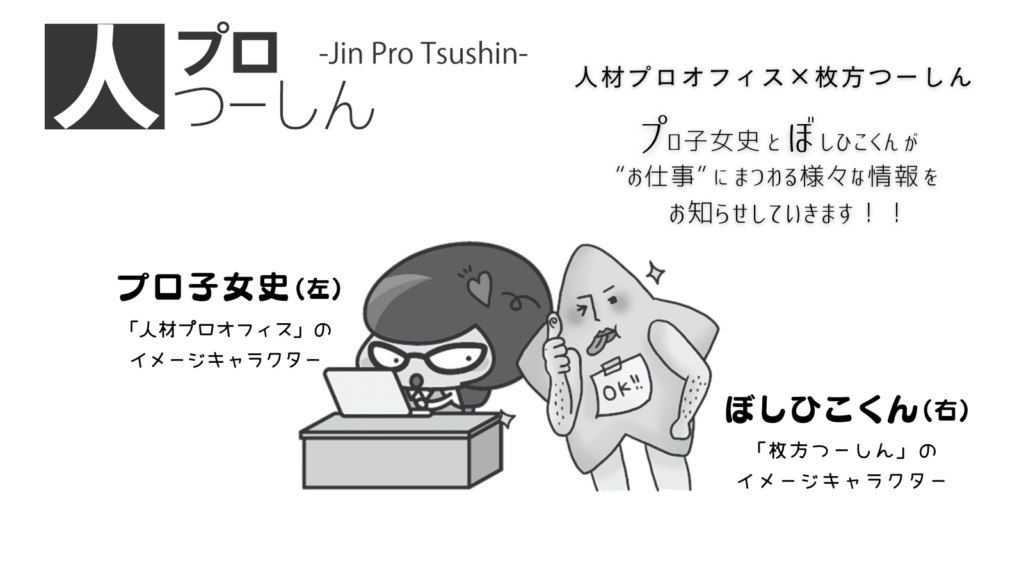
■地震のメカニズム
プロ子(以下:プ)「今回は地震が来た時の企業の対応について考えようと思うの」
ぼしひこ(以下:ぼ)「まだ東北地方太平洋沖地震から5年しか経ってないのに熊本地震が来たし…。日本は地震の多い国ってことを改めて認識した人も多いと思うな…」
プ「そうね。日本で地震の多い理由は知ってる?」
ぼ「プレートっていう地球の表面を覆ってる大きな岩の層が関係してるって聞いた気がするけど詳しくは…」
プ「日本周辺は4枚の大きなプレートがぶつかり合っている地域なの。地震の基本的なメカニズムを説明すると、海側のプレートは1年間に数センチ程度ゆっくりと沈み込んでいくの」
ぼ「反対に陸側のプレートが押し込まれていくってこと?」
プ「その通り。陸側のプレートが海側のプレートに引きずり込まれていって歪んでいくの。そして歪みに耐えられなくなった時に跳ね上がる」
ぼ「その跳ね上がりが地震になるってことか…」
プ「だから地震は『必ず起こる』もので避けられない仕組みなの」
■海溝型地震と内陸型地震
ぼ「今回の熊本地震も同じ仕組み?」
プ「いえ、違うわ。東北地方太平洋沖地震はさっき説明した『海溝型地震』だけど熊本地震は『内陸型地震』になるわ」
ぼ「内陸型地震? 確かニュースでは『断層』って言葉がよく出てきてたと思うけど…」
プ「今回は陸側のプレートがプレート移動によって圧縮され、日本列島をのせている陸のプレート内の岩の層『断層』が壊れてずれることにより発生したの」
ぼ「海溝型地震とはどう違うん?」
プ「海溝型地震は内陸型地震は、地下約5~20㎞ぐらいの浅い所で起きるから今回の熊本地震のような大きな被害をもたらすの。そしてもうひとつ、内陸型地震は海溝型地震に比べて予測が困難とも言われているわ」
ぼ「南海トラフ地震とか首都圏直下地震とか、起こる可能性はずっと言われてるもんな…」
プ「大地震が起こらないことを心から願うけれど、起こった時にどう行動すべきか、どう準備しておくべきかを考えておくことは決して無駄にはならないと思うわ」
■企業としての対応
ぼ「地震は避けられへんとしたら…やっぱり備えるしかないってこと?」
プ「そうね。参考までに人材プロオフィスの取引先での備えを紹介するわ」
ぼ「お願いします」
プ「震度〇以上(各社で設定可能)の地震があれば、企業の従業員へ一斉にメールが届き、企業コード・暗証番号等入力すると、安否確認ができるセコムのシステムを導入している取引先があるわ」
ぼ「なるほど」
プ「安否確認・被害状況など報告できるシステムで、まとまった情報の報告が企業の担当者へ届くシステムよ。同様のシステムが、アルソック・東洋テックなどにもあるわね」
ぼ「色んな仕組みがあるんやね」
プ「システム導入は費用や時間がかかるにしても、災害が起こった場合は…
避難場所を決めておく
(例:避難場所は、建物の被害、土砂災害・堤防決壊などの影響を受けない場所を選ぶ。さらに、〇〇(場所)の〇〇前のように具体的に決めておく方が良いでしょう。)
避難のルールを決めておく
(例:災害直後は混乱していて指示を出すことは困難。避難場所へ従業員が自発的に行動できるように行動基準を決めておく)
この2つを決めておけば、従業員が迷うことなく避難ができ、避難状況の確認ができると思うわ。もちろん状況に応じて臨機応変な対応は必要だと思うけれど」
ぼ「NTTの災害ダイヤル(171)とか、各携帯電話会社も災害伝言板などのサービスを実施してるから、使い方も一度確認しておいた方がいいね」
プ「何よりもまずは『自身の安全確保』そして、あらかじめ決めておいた『待ち合わせ場所』『連絡方法』に沿って行動することが大事ね」
ぼ「備えあれば憂いなし。この機会に一回ちゃんと考えてみるわ」
プ「そうね。皆さんももしもの時の対応方法をこの機会に話し合ってみてくださいね」